娘が3歳で、年少クラスから保育園に通いだした春。
毎朝のように、保育園の玄関で、「行きたくない!!パパがいい!!」と泣いて私にしがみつき、無理やり引きはがして預ける日々が続いていました。
朝の忙しい時間に泣かれると、ついこちらも焦ってしまいます。
でも、それ以上に「ここまで嫌がる娘を無理に預けていいのか…」と、私自身も心が締め付けられる思いでした。
そんな中で、ふとしたことから“お気に入りのぬいぐるみ”を登園に連れていったことで、娘の様子が少しずつ変わっていきました。
この記事では、同じように登園を嫌がる子どもがいる方に参考になるように、私の体験と実際の対処法を書いてみたいと思います。
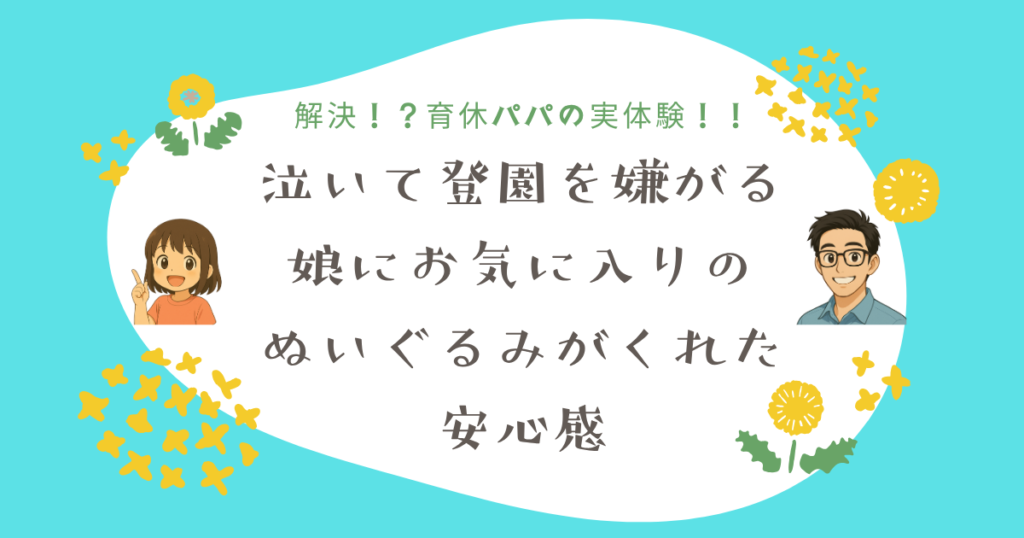
突然始まった「保育園イヤイヤ期」
娘が保育園に通い始めたのは、年少(3歳)の春でした。
息子も同じタイミングで1歳児クラスに入園。
ただ、息子はまだあまり状況がわかっていなかったのか、つられて泣くことはあっても、娘ほど強く嫌がる様子はありませんでした。
娘はというと、最初こそ少し緊張しながらも登園していましたが、ある日を境に急に「保育園に行きたくない」と泣き出すように。
当時はちょうどコロナウイルスが流行していた時期で、保育園では「玄関でバイバイ」の対応が基本。
親は園内に入れず、先生に荷物と子どもを一緒に預ける形でした。
でも娘は、玄関で私にしがみついてなかなか離れません。
「パパがいい!行きたくない!!」と、家では聞いたことのない大きな声で泣き出します。

最初はなだめてみるものの、私もすぐに仕事に行かなければならず、次第に焦りが出てきて、結局、無理やり引きはがすような形で先生にお願いして、泣き叫ぶ娘を預けることに…。
登園後、仕事に向かう道中、心がずーんと重たくなっていました。
「卒園まで、毎日これが続くのかなぁ。しんどいなぁ」
「ここまで嫌がる娘を、本当に無理して預ける必要があるんだろうか…」
そんな思いが頭の中をぐるぐる。
娘の泣き声が通勤中ずっと耳に残り、私まで憂うつになる日々でした。
藁にもすがる思いで「コリラックマ作戦」を決行
娘には、0歳のときから一緒に寝たりしている、お気に入りのコリラックマのぬいぐるみがあります。
ある日、家で遊んでいたとき、そのコリラックマを、少し変な声で喋らせていたら、娘がすごく笑っていて、「これは使えるかも」と思ったんです。
藁にもすがる思いで、次の日の朝、そのコリラックマのぬいぐるみを車に乗せて登園に向かいました。
いつもどおり玄関の手前あたりでぐずりだす娘。
そこで、周りの目は気になるものの、家で遊んでいたときと同じように、コリラックマのぬいぐるみを喋らせてみました。

「コリ(ぬいぐるみの名前)と一緒にいこ?おててつなご?」
そういうと、娘は泣き止み、うなずいて、コリラックマのぬいぐるみと一緒に歩き始めたんです。
コリが“安心のパートナー”に
先生に荷物を預け、いつもなら私にしがみついてくるタイミングで、
「コリと握手でバイバイしよ」
と声をかけると、娘はぬいぐるみの手を握って「バイバイ」と言い、先生のもとへ笑顔で行ってくれました。
泣かずに笑顔で行ってくれたことが、あまりにうれしすぎて、すぐに妻にLINEしました。
もちろん、日によっては、うまくいかない日もありました。
でも、それ以降、娘のぬいぐるみやお気に入りのおもちゃを“喋らせる”スタイルが、我が家の定番になりました。
不安な朝、初めての場所、ちょっと緊張している場面――
娘にとって、ぬいぐるみが“心のお守り”のような存在になっていったように思います。
今振り返って思うこと
慣れない環境に入ることは、大人でも不安です。
子どもなら、なおさらだと思います。
そんなときに、一つでも「心の安定剤」になるものを持たせてあげるだけで、状況が少し変わることがある。
そして何よりも、その不安な気持ちに共感してあげることが、親として大事なことなのだと気づきました。
今では毎晩、寝る前に娘にこう伝えるようにしています。
「今日も頑張ってくれてありがとう。お疲れ様。」
子どもは子どもなりに、毎日ちゃんと頑張っている。
そのことを当たり前だと思わずに、感謝して、その思いを直接言葉で伝えるようにしています。
まとめ|子どもに“安心”を届けるために
「保育園に行きたくない」
その気持ちの奥には、きっと言葉にできない不安や戸惑いがあるんだと思います。
そんなときは、子どもが“安心できる存在”をそっとそばに置いてあげること。
そして、「あなたの気持ちわかるよ、ちゃんと受け止めてるよ」と共感してあげることが、親としてできるサポートなのかなと感じています。
ぬいぐるみ、ハンカチ、タオル、パパやママの声――
みなさんの子どもに合った「お守り」が、きっとあるはずなので、一緒に見つけてあげてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
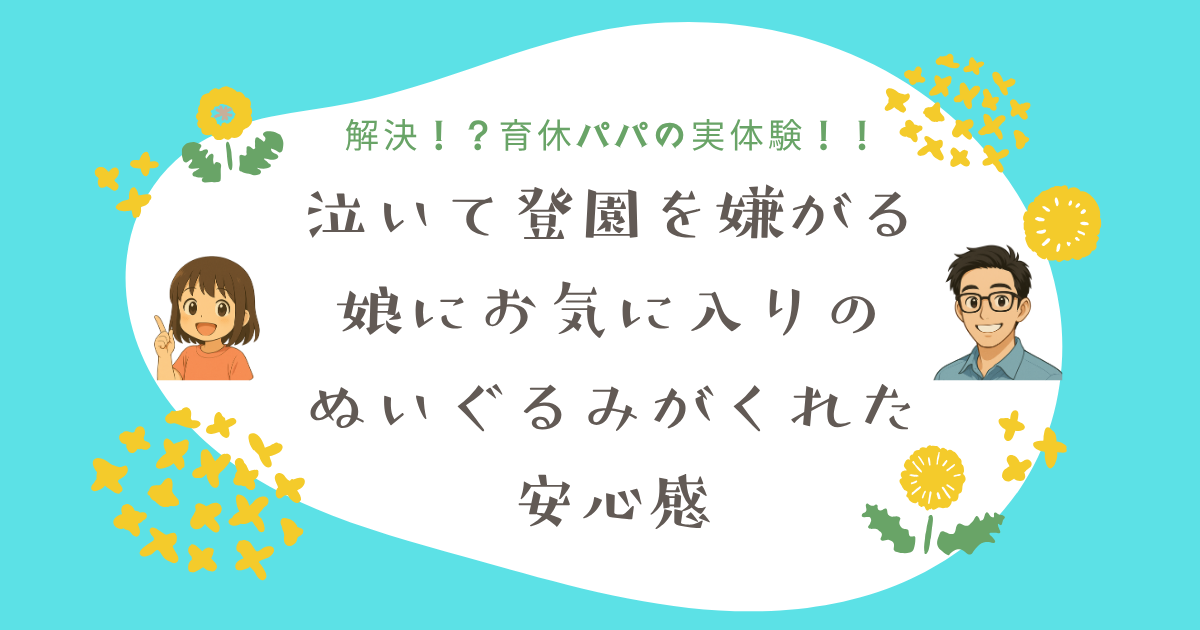
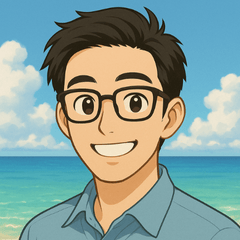

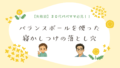
コメント